バス業界に関わる情報を専門的に扱う編集部です。現役運転手・バス会社・キャリア支援の専門家など、複数の視点をもとに記事を企画・編集し、働き方や制度を中立的に分かりやすく伝えることを心がけています。運転手さん自身が納得して判断できる情報提供を目指しています。
バス運転手になるためにはどの免許が必要?費用や時間はどれくらいかかる?

「バスの運転手はどうやったらなれるの?」「免許ってどれを取ればいいの?」「免許取得までにかかる費用や時間ってどれくらい?」など疑問に思ったことはありませんか?
この記事ではバスの運転手になるために必要な免許や、かかる費用について詳しく解説します。
バスの運転手になるために必要な免許
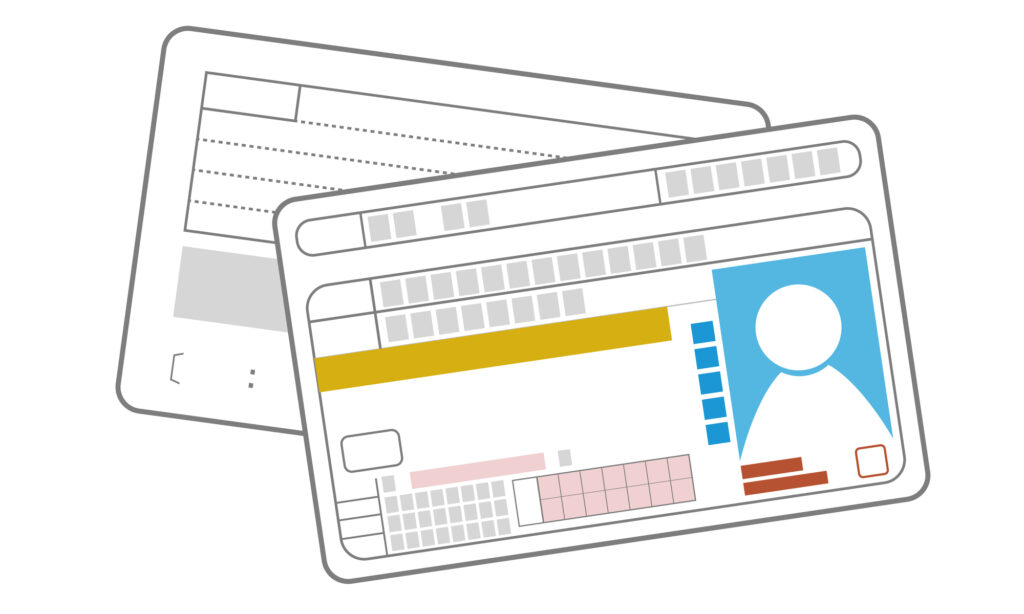
バスの運転手になるためには、第二種大型免許を取得しなければなりません。正式名称は「大型第二種自動車免許」。街でよく見る路線バスや観光バス、高速バスを運転するために必要な免許です。
第一種運転免許と第二種運転免許の違い
第一種運転免許は営利目的でなく、私的に自動車やバイクを運転することを目的としたものです。自家用車を運転するなら一種免許を取得すれば十分ですよ。
第二種運転免許は旅客運送業務を行うために必要な免許です。タクシーやバスなど、お客さんを乗せて運転するためには、この免許を取らなければなりません。
第二種大型免許の取得方法と条件
第二種大型免許の取得方法
第二種大型免許は、免許センターで一発試験を受けるほか自動車教習所に通うことで取得が可能です。
第二種大型免許を取得できる教習所は限られているので、事前に調べておきましょう。
免許の取得条件
第二種大型免許を取得するためには、以下の受験資格を満たしている必要があります。
- 21歳以上
- 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を持っていて、経歴が通算3年以上
- 上記または、他の(大型以外の)二種免許を持っている
- 視力:両眼で0.8以上かつ、片眼それぞれ0.5以上(メガネやコンタクトも可)
- 深視力(※):3回検査の平均誤差が2cm以下
- 色彩識別能力:赤・青・黄色の識別ができる
- 聴力:10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる(両耳)
※深視力…遠近感や立体感を判断する目の能力
ただし令和4年の道路交通法改正により、受験資格が一部緩和されました。通常教習に追加して、特別な教習(受験資格特例教習)を修了することで「19歳以上かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上」であれば、第二種大型免許の取得が可能です。
特別な教習は以下の3種類があります。
- 年齢課程…免許取得条件を19歳以上に引き下げる教習
- 経験課程…各免許の取得要件の運転経験年数を1年以上に引き下げる教習
- 年齢+経験課程…年齢と運転経験どちらの条件も引き下げる教習
なお特別な教習が受けられる教習所は限られています。各都道府県警察の窓口で、対応可能な教習所の確認ができますよ。
第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)|警察庁Webサイト
またAT限定の免許しか持っていない方は、以下の2つの方法で限定解除をする必要があります。
- 第二種大型免許の教習前にAT限定を解除しておく
- 第二種大型免許の教習と同時にAT限定を解除する
しかしバスやトラックの運転手不足を背景に、2026年4月以降、大型・大型二種・中型・準中型・中型二種にも、AT限定免許を順次導入する方針を警視庁が発表しました。時間や金銭面での負担が減るはずなので、これからバスの運転手になりたい人にとっては朗報ですね。
なお中型二種は26年4月から、大型二種は27年10月から導入される予定です。
バスによって取る免許は違う?

バスの大きさによって取得する免許が変わります。以下の表を参考にして、事前に確認しておきましょう。
| | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 運転できるバス | なし | なし | マイクロバス | マイクロバス、中型バス、大型バス |
| 車両総重量 | 3.5t未満 | 7.5t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
| 最大積載量 | 2t未満 | 2t以上4.5t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上30人未満 | 30人以上 |
中型8t限定と準中型5t限定免許は、車両総重量や積載量に違いがありますが、乗車定員は普通免許と同じでバスは運転できません。
なおバス運転手になるために、必ずしも大型免許が必要というわけではありません。例えば幼稚園や習い事教室などに務めており、送迎でマイクロバス以下の車両しか使わないのであれば、中型免許で運転が可能です。10人以下であれば普通免許でも可。自分の就職先や運転するバスの大きさに合わせて免許を取りましょう。
バスの免許を取るのにかかる費用

教習所に通う場合、第二種大型免許の取得費用は約40~60万円です。ちなみに普通免許も持っていない場合、まずはそちらの取得が必要なので、全部で約90万円はかかると考えておきましょう。
補助金(給付金)について
バス会社によっては、第二種大型免許の取得費用を負担する制度(大型二種免許取得支援制度)を設けています。
またハローワークがキャリアアップと再就職の支援として特定一般教育訓練給付金制度というものを設けています。受講費用(第二種大型免許の教習費用など)の40%(上限20万円)を給付金として貰うことができるんですよ。
なお以下の条件を満たす方が、受給の対象です。
- 雇用保険を抜けて1年以内に受講する方
- 雇用保険に入っていた期間が3年以上の方(初回は1年以上)
- 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、最終受給日から受講日までに3年以上経過してる方
<参照>厚生労働省リーフレット:令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます
この制度を使える自動車教習所は限られているので、以下のサイトから検索してみてくださいね。
<教育訓練制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム>
バスの運転手になるには何年くらいかかるの?

第二種大型免許を取るまで
普通免許等を持っていない人は、第二種大型免許を取得するまで最短でも1年半程かかります。すでに何かしらの免許を持っている人であれば、最短1ヶ月程度で第二種大型免許の取得が可能です。
教習所の期間は保有免許によって変わりますが、普通免許をお持ちの場合、通いの教習所なら最低でも1ヶ月以上、合宿であれば15泊程です。
独り立ちするまで
バス運転手として独り立ちするまでは、半年から1年程かかるでしょう。
入社してから数週間は、バス運転手として基本的な研修を行います。内容は座学やバス点検の仕方、訓練場での運転研修など、バス会社によって様々です。
基本的な研修が終わると、次は実践訓練がスタート。先輩運転手がマンツーマンで指導を行い、実際にお客さんを乗せて運行をします。全ての訓練を終えて最終試験をクリアすれば、一人前の運転手の仲間入りです。
バスの免許を取るのって難しい?

第二種大型免許は、ほかと比べて取得が難しいです。令和4年の運転免許統計によると第一種普通自動車免許の合格率は74.5%、第一種大型免許の合格率が95.0%なのに対し、第二種大型免許の合格率は63.6%と低いです。
普通車と比べて大型車は死角が多かったり、距離感が掴みにくかったりといった理由から、高度な運転技術が必要です。またお客さんを乗せて走るため、接客の知識も求められます。
とはいえ令和3年と4年を比べると、第二種大型免許の合格率はおよそ4ポイントアップしており、決して難攻不落な試験というわけではありません。
一発試験ではなく教習所に通い、技術と知識を身につけてから受験すれば合格できるでしょう。
<参照>運転免許統計
<まとめ>バスの運転手になるためには第二種大型自動車免許が必要
- 第二種大型免許は「21歳以上、普通免許等の保持期間が3年以上」であれば取得が可能
- ただし特別な教習を受けることで、「19歳以上、普通免許等の保持期間が1年以上」に条件が引き下げられる
- 第二種大型免許の取得には約40~60万円程度かかるが、バス会社の免許取得支援制度や国による給付金を利用できる
- 免許取得から一人前のバス運転手になるまで、最短で半年ほどかかる
- 第二種大型免許の取得は難しいので教習所でしっかりと学ぶべし
バス運転手の達人では、第二種大型免許の補助が出るバス会社の求人案件も多く掲載しています。自分にあったバス会社さんを探してみてくださいね。

